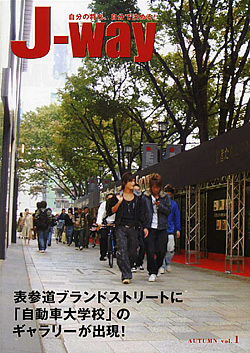2006年度のニュース
平成17年度全国統一模擬(1級口述)試験の結果報告
1.試験実施校
25校
2.種目別申請者数及び受験率等
| 種目 | 申請者(名) | 受験者(名) | 受験率(%) |
|---|---|---|---|
| 1級口述 | 334 | 304 | 91 |
3.総合得点の全国平均
| 問題1 | 問題2 |
|---|---|
| 7.23点(10.0点) | 7.67点(10.0点) |
注1)( )内は昨年度の得点です。

平成17年度全国統一模擬試験(1級小型自動車)の結果報告
1.試験実施校
20校(2年対象)
(注)1年生を対象に受験された学校も有りましたがデータからは除外してあります。
2.種目別申請者数及び受験率等
| 種目 | 申請者(名) | 受験者(名) | 受験率(%) |
|---|---|---|---|
| 1級小型自動車 | 334 | 326 | 97.6 |
3.総合得点の全国平均
31.5点 (33.4点)
注)満点得点は50点です。なお( )内は昨年度の値です。
4.分野別得点の全国平均
| 1.エンジン | 2.シャシ | 3.故 障 | 4.環 境 | 5.法 令 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 (10.0) [15] |
9.0 (8.4) [15] |
6.8 (7.8) [10] |
3.1 (4.6) [5] |
3.2 (2.6) [5] |
注1)( )内は昨年度の得点です。
注2)「 」内は分野別得点です

平成17年度全国統一模擬試験(二級・車体)の結果報告
1.試験実施校
| 2級ガソリン自動車 | 54校(53校) |
|---|---|
| 2級ジーゼル自動車 | 52校 (49校) |
| 自動車車体 | 14校 (14校) |
※( )内は昨年度の値です。
2.種目別申請者数及び受験率等
| 種目 | 申請者(名) | 受験者(名) | 受験率(%) |
|---|---|---|---|
| 2級ガソリン自動車 | 9593(9729) | 9282(9445) | 96.8(97.1) |
| 2級ジーゼル自動車 | 9368(9439) | 9068(9154) | 96.8(97.0) |
| 自動車車体 | 481(456) | 449(435) | 93.3(95.4) |
3.総合得点の全国平均と分野別得点の全国平均
| 項目 | 2級ガソリン | 2級ジーゼル |
|---|---|---|
| 総合 | 26.9(28.0){40} | 25.4(24.5){40} |
| 一般工学 | 3.6(3.7){5} | 3.5(3.3){5} |
| エンジン | 7.7(9.0){12} | 7.8(7.3){12} |
| シャシ | 9.0(9.1){13} | 7.7(7.9){13} |
| 電気 | 3.1(3.0){5} | 3.2(3.0){5} |
| 法令 | 3.5(2.9){5} | 3.2(2.8){5} |
| 項目 | 自動車車体 |
|---|---|
| 総合 | 26.2(27.1){40} |
※( )内は昨年度の値です。 { }内は分野の満点得点です。

平成18年度JAMCA全国統一模擬試験日程
| 二級&車体 | 平成19年1月13日(土) |
| 一級【筆記】 | 平成19年2月6日(火) |
| 一級【口述】 | 平成19年2月13日(火) |
| 三級 | 平成19年3月3日(土) |
第29回経営研究会
JAMCAの第29回経営研究会が9月9日、東京ガーデンパレス(東京・湯島)で、会員校36校から会員48名を迎え、来賓3氏の列席のもと開催されました。
冒頭の挨拶で中川会長は、少子化やフリーター・ニートが取り沙汰される社会情勢の中で、一級自動車整備士制度を軸とする協会諸施策の推進を揺るぎ無く進めることの重要性と、整備士イメージを変える広報活動が望まれることなどを訴えました。一級対策委員会による模擬試験の拡充計画や、この日プレゼンで紹介されたJAMCA初のフォトコンテストの実施などはこうした主張とのリンクを窺がわせるものでした。
続く講演会では、国土交通省・小島信治整備課補佐、文部科学省・澤川和宏専修学校教育振興室長が整備事業の現況と高度専門士の称号について講演しました。
懇親会の場には、国土交通省・清谷伸吾整備課長、文部科学省・平松昌弥室長補佐、日車協連・丸山憲一会長も姿を見せて長らく談笑の輪の中心に収まり、予定時間オーバーの盛会のうちに大締めを迎えました。

第4回一級自動車整備士指導員講習会

第4回の一級自動車整備士指導員講習会が8月22—24日の3日間、千葉県船橋市のセミナーハウス「クロス・ウェーブ」で開かれ、17校から26名が受講しました。修了判定試験を含めて受講時間の合計は20時間、講師陣8名の内6名は例年通り会員校の先生が担当しました。講師の多くは独自のサブテキストを併用するなど、決められた時間内に密度の濃い講義を展開。受講生も暑いさなか集中力を切らすことなく無事全日程をクリアしました。同講習会で日整連から資格授与された総数は昨年時点で421名、今回の判定結果が明らかにされるのは9月の中旬頃となります。
第9回教職員夏季研修会
充実の教職員夏季研修会

(猛暑を忘れた5日間)
今年も静岡県新浜松市のウェルサンピア浜松を会場にJAMCA主催の教職員夏季研修会を7月25日より5日間コースで開催、応募した16校27名の中堅教職員が参加しました。
研修プログラムは教育心理や問題解決手法などを中心テーマにグループワークを多用する既定の枠組みに沿って行われたが、研修生にとっては日頃の悩みや問題を俎上に乗せて研鑽をはかる好機、熱のこもった討議や団らんの輪が研修時間外にも続きました。
初日と最終日に組み込んでいる理事講話のパートを、今年はJAMCAの正副会長でなく古澤理事と中山理事に依頼しました。古澤理事は「私が期待して求めている教職員像」、中山理事は「教育と共育」というタイトルで、それぞれ豊富な体験を踏まえて講話を下さり、研修の前後を飾ることとなりました。
研修生からは日課として「所感の提出」を求めているが、「教育現場で活かしたいツールがたくさん得られた」、「5日間で築いた先生同士のきずなが財産となった」といった感想を頂いています。
第43回通常総会
JAMCA第43回通常総会は6月9日、佐世保市ハウステンボス町のホテル ヨーロッパで開催されました。国土交通省、文部科学省の担当官ほか、日整連、日車協連から来賓を迎え、出席校は58校(うち委任状24校)、総出席者数は51名でした。
総会議事では平成16年度の事業報告と収支決算、平成17年度の事業計画案と収支予算案が承認され、更に現行会則に新規加入に関する第6条を新設したいとする理事会の会則改正案が承認されました。
また、任期満了に伴う役員改選では役員全員が再選され、新理事による理事会で会長に中川裕之氏、副会長に斎木寛治氏、理事顧問に小倉基義氏が再選されたことが報告されました。中川会長は再選後の挨拶で、時の動きについて触れたいとして、平成16年度中に大学校名を名乗ったことの制度的意味、学生進学の選択肢としてより一層一級整備士の数を増やしていくことの必然性について述べたあと、産業界のための教育を目指すことより、自主的に産業界に貢献する心構えを持たせる教育が大切と考えると結びました。
総会を終了したあと、一級対策委員会に対して感謝状の贈呈がなされました。
これは平成16年度を通じて一級登録試験に焦点を定め、問題集作成や一級模擬試験を計画・実施したことがタイムリーで有効な授業支援となったとJAMCAから等しく評価されたためです。
総会に続く講演会では、国土交通省の内藤政彦整備課長が検定試験結果、法令順守姿勢(コンプライアンス)の重要性、自動車検査・点検整備制度の去就について、文部科学省の手塚健郎専修学校教育振興室長補佐が専修学校の課題や平成17年度予算などについてそれぞれ講演しました。また、国土交通省の川島孝夫整備課長補佐、日整連の関口久男試験部長、日車協連の崎本芳雄常務理事他から挨拶を頂きました。
懇親会は斎木寛治副会長の主催者挨拶に始まり、川島孝夫整備課長補佐の発声で乾杯、小倉基義理事顧問の中締めと進み、途中で蛇踊りが入るなど和やかな飲食、歓談が続きました。

JAMCA会員校 学校名変更
下記会員校が校名変更しました。
()内は旧校名
平成17年1月13日付 1校
- 専修学校群馬自動車大学校 (群馬自動車整備専門学校)
平成17年2月15日付 1校
- 専修学校東京自動車大学校 (東京自動車整備専門学校)
平成17年4月1日付 13校
- 日産栃木整備専門学校 (日産自動車整備専門学校)
- 日産横浜整備専門学校 (日産メカニック・ビジネス専門学校)
- 日産京都整備専門学校 (日産学園京都自動車工業専門学校)
- 日産愛知整備専門学校 (日産愛知自動車工業専門学校)
- 日産愛媛整備専門学校 (日産愛媛自動車工業専門学校)
- 専門学校花壇自動車整備大学校 (花壇自動車整備専門学校)
- 専門学校関東工業自動車大学校 (関東工業専門学校)
- 中央自動車大学校 (中央自動車技術専門学校)
- 横浜テクノオート専門学校 (神奈川自動車専門学校)
- 専修学校中部国際自動車大学校 (土岐自動車工学専門学校)
- 専門学校静岡工科自動車大学校 (静岡工科専門学校)
- 専門学校広島自動車大学校 (広島自動車整備専門学校)
- 専門学校広島工学院大学校 (広島工学院専門学校)
平成17年度行事日程
- 総会
-
平成17年6月9日(木)〜10日(金)
会場:佐世保市ハウステンボス「ホテル ヨーロッパ」 - 理事会
-
- 第1回 平成17年5月
- 第2回 平成17年6月9日(木)
- 第3回 平成17年9月
- 第4回 平成17年12月
- 第5回 平成18年3月
- 監査会
- 平成17年5月12日(木)
- 教科書編集委員会
- 平成17年6月
- 第9回教職員夏季研修会
-
平成17年 7月25日(月)〜7月29日(金)
会場:浜松市・ウェルサンピア浜松 - 第4回一級指導員講習会(日整連主催、JAMCA主管)
-
平成17年 8月22日(月)〜24日(水)
会場:船橋市・クロスウェーブ - 第29回経営研究会
-
平成17年9月9日(金)
会場:東京ガーデンパレス - JAMCA全国統一模擬試験
-
一級(筆記) 平成18年2月7日(火) 〔一級課程1・2年生〕 一級(口述) 平成18年2月14日(火) 〔一級課程1・2年生〕 二級・車体 平成18年1月14日(土) 〔二級課程2年生〕 三級 平成18年3月4日(土) 〔二級課程1年生〕